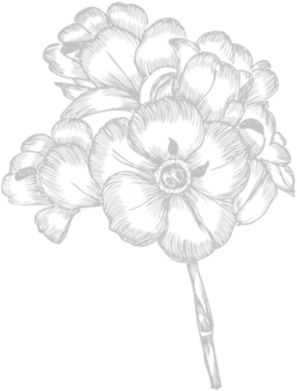こんにちは。ジャパネシアのタイキです。
インドネシア語を学ぶ人にとって、「長文読解」って避けられないステップですよね。
特に検定(Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia)を受ける人にとっては、C級以上の試験で一気に読解の壁が立ちはだかると思います。
僕も、まさにそこでつまずいてきた人間です。ってか今でもむずかしーーー!って思ってます。笑
辞書を引いて、ひたすら訳してきた。でも…
正直に言うと、僕は昔、「とにかく訳せ!」の姿勢で読解をしていました。
- 辞書を片手に1文ずつ追いかける
- わからない単語を逐一調べる
- 一語一句、日本語に置き換えることに集中する
それを何年もやってきた。
でもあるとき、ふと気づいたんです。
「全部訳したはずなのに、なんか分かった気がしない…」
なぜ?――その原因は“背景知識”だった
知らない単語は調べた。文構造も確認した。
それでも文章の“流れ”がわからない。
その原因は、背景知識がなかったからでした。
たとえば、こういうことです。
📌 例:ニュースや評論の「型」を知らないと迷子になる
インドネシア語の長文には、
テーマごとに**「お決まりの展開」や「定番の論点」**があります。
🔧 例1:鉱山掘削
- 初めに:採掘の概要や場所
- 次に:近隣住民との衝突や環境問題
- 結論に:政府の対応・企業の責任
🌿 例2:森林伐採
- 原因:違法伐採や外資系企業の開発
- 結果:洪水や生態系破壊
- 論点:地元住民との対立/国の規制の甘さ
📱 例3:デジタル化社会
- 背景:AIやテクノロジーの進化
- 問題:プライバシー・デジタル格差
- 議論:人間性と効率性のバランス
こういった「構造の予測」が頭にあるかないかで、読むスピードも理解度も全然違ってくるんです。
逆に、背景知識があるとこう変わる!
同じ文章でも、「この流れ、知ってるぞ」と思えた瞬間、読解の負荷は一気に減ります。
- 分からない単語が出ても文脈で想像できる
- 書かれている事実がどういう立場から書かれているかが分かる
- 質問に対して「どこを見ればいいか」がすぐ見える
一文ずつが「点」でしかなかった僕に足りなかったのは“流れ”
僕は昔、インドネシア語→日本語に変換する作業ばかりやっていたから、
いつまでも「文」が「点」としてしか見えてなかった。
背景知識を知らずに読んでいたから、
“点”が“線”にならず、ずっと遠回りしていました。
だから、この教材を作りました。「長文読解+背景知識」
この教材は、ただ長文を載せて終わりじゃありません。
1本1本の記事に対して、
- その背景や時代背景
- よく出てくる語彙と論点
- 読む前に押さえておくと楽になる知識
などを、日本語で簡単に整理してから読解に入れるようになっています。
構成はこんな感じです:
🧠 1. 背景知識(テーマ概要)
- 何の話題か
- この分野でよく使われる語彙・表現
- 論点はどこにありがち?
📄 2. 長文(本番形式)
- 検定に近い文体・長さ・語彙レベル
- 一部は実際のニュースや評論を元に構成
❓ 3. 理解確認問題(検定対策にも対応)
- 正誤問題
- 要点整理
- 推論型の問い
とりあえず、一つサンプル動画を見てみてくださいね♪
こんな人にこそ使ってほしい
- B級やA級を目指しているが、長文で止まる人
- 一文一文訳してるのに、全体像が見えない人
- 語彙を覚えても文章が“入ってこない”人
- 時事やニュース系が出ると一気に不安になる人
💡 「詰まったパイプ」は、少しずつ開通する
読解って、最初は水が流れないパイプみたいなものです。
- 単語が詰まり
- 構文が詰まり
- 背景知識がないから、文の方向も分からない
でも、ひとつひとつ詰まりを取っていくと、急に水がスーッと流れ始める。
この教材は、その“詰まりを取る”サポートをしてくれる存在です。
まとめ|読解は知識と経験の“融合”
- 単語を覚えるだけでは足りない
- 文法だけでは読解は完成しない
- 文脈・背景・テーマの理解があって、読めるようになる
「訳せる」と「理解できる」は、似て非なるもの。
あなたには、僕と同じ遠回りをしてほしくない。
読解に悩んでいるなら、この「長文読解+背景知識」をぜひ試してみてください。
読むことが、少しずつ“見える”ようになってくるはずです。
そして、JLCでは中級読書会を僕とインドネシア人講師がペアで担当しておりますので、ぜひこちらにも気軽にご参加くださいね。